
2023.05.15
5月はマリア様の月です。
昨年のマリア様の祝いの時には、
子ども達にこんな話をしました。
今日はマリア様のために沢山の花を
持ってきてくれましたね。
マリア様もとても喜んでくださっていますね。
今ここにある花はとてもきれいだけれど、
時間がたつと枯れてしまいますね。
枯れてしまったらどうしましょう。
「また持ってくる」「枯れないように水を入れてあげる」
等々意見が出ました。
ここにある花もとてもいいけれど、
枯れない花もあるの「え~っ!作った花?」
「折り紙の花?」それはね、心の中にさいた花なの
「…?」どんな時に心に花が咲くと思う?
「う~ん…」それはね、
お友だちが泣いていた時にどうしたのと
優しく声をかけてあげた時、
一緒にやろうと仲良くできた時、
ありがとうと言えた時、ごめんねと言えた時、
皆が周りの人のために優しい心をつかった時、
心の中に花がさいて、その花はずっと枯れないで咲いているの。
1人ひとりの心の中に花が沢山咲いたら、
心の中にいるマリア様はいつも花を見ていられるね。
そうしたらとっても嬉しいって
喜んでくださると思うの。
だから5月のマリア様の月には心の中に
沢山の花を咲かせましょうね。と。
先日こんなことがありました。
朝の門で『シクシク…』している妹と、
一刻も早く部屋に行きたい兄。
門でお母さんや先生が妹も一緒に連れていってと頼んでも、
毎日先に行ってしまう兄…。
(早く行きたい気持ちはよくわかります)
ちょうど先週、その子が職員室にお祈りシールをもらいにきたので、
『朝、妹と一緒に部屋まで行ってあげてくれないか』
と頼んだところ、「うーん、考えてみる」と
あまり乗り気でない返事が返ってきました。
そこで「頭で考えないで、心で考えてみて」
と伝えました。「わかった」と言って出ていき、
ほどなくして戻ってくると、
職員室の入り口でひょっこり顔を出して
「考えた!」と一言だけ言って去っていきました。
どう考えたのだろうと聞きたい気持ちを
抑え翌日の朝を待ちました。
迎えた翌朝、どんな様子だったか
門の先生に聞いてみると、
妹と手をつないで年少の部屋まで
一緒に行ってくれたとのこと。
どのタイミングで声をかけようかと思っていると、
ちょうど当番の仕事で職員室にやってきました。
「心で考えて、妹のために頑張ってくれたんだね。
ありがとう」というと「面倒くさいけどね!」と
一言残して職員室を後にしました。
きっとそれが本音でしょう。
でも早く行きたい気持ちと妹の気持ちの両方を考え、
大事にした方がよいと思ったことを選んで
行動できたことは本当にすごいことです。
まさに心に花が咲いた時だったと思います。
私は心で考えてと言っただけなのですが、
それが通じたというのは彼の心が育っていたということ。
本当に嬉しい場面に出会わせてもらえました。
今年もマリア様の月がやってきます。
子どもたちの素直な心に負けないように、
私も心の花をたくさん咲かせていきたいと思います。
園長 玉井史恵
2023.02.01

この間廊下を歩いていた時、
私の顔をみるといつも静かに近寄ってきて
自分の服を手渡す(手伝ってと無言のお願いをする)年少さん。
この日は近づいても私に気が付かないほど
真剣に自分の脱いだ遊び着を黙々と畳んでいました。
しばらく見ていましたがそれでも気づかず
袋を入れ終わるまで一人でやりきりました。
ここまでくるのに約1年、
ようやく自分の力でできる喜びを感じるまでに
費やした努力は担任が一番知っていることでしょう。
私の横には嬉しそうに見守る担任の姿がありました。
友達とはいいけれど、大人と話すことがとても苦手で、
遊んでいるときは話してくれるのに、
面と向かうと何も言えず黙って目で訴え、
私たちの声がげに涙目でうなずくことがやっとだった年長さん。
この間初めて「お箸忘れたから貸してください」と
私の目を見て言葉を交わしてくれました。
この日まで恥ずかしいという気持ちと
どれほど葛藤しながら過ごしてきたことでしょう。
この一言に込められた思いや、努力を想像した時、
胸があつくなりました。
私に用があって(ブロックで作ったものを見せに)
来てくれた年長さん。
来客中だった様子を見て何も言わずに黙って部屋に帰り、
時間が経ってから「もう入ってもいい?」と
聞いてから職員室に入ってきました。
状況を見て、今は園長先生だめなんだなと判断し、
行動できるなんてすごいことです!
また先日、延長保育に上がっていく時
珍しく泣いていた年長の女の子。
「どうしたの」と声をかけ手を広げると
黙って私の膝の上に乗りしばし涙…。
その姿を見た友達が近寄ってきて
理由を聞くわけでもなく静かに「一緒に行こう」と
手を差し伸べてくれました。
泣いていた女の子はその手を取り
一緒に階段をあがっていきました。
言葉ではなく差し伸べられた手から、
とても温かい心を感じたのは
私もその女の子も同じだったことでしょう。
このように日々の生活の中で
嬉しいできごとに出会えた時の幸せな気持ちは、
後で思い出しても心の中が温かくなります。
そして一人ひとりの行動の裏にある気持ちを考えた時、
お金で手に入れた物からは決して得ることのできない
大きな幸せを感じます。
『見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ』
金子みすずさんは昼間の星は目に見えない。
でもそこに存在している大切なものと詩にしています。
『大切なものは目に見えない。かんじんなことは、
心の目でみないとみえないんだよ』(星の王子さまより)
目に見えて育った姿の中にある『お子さんの心』
皆さんには見えていますか?
これからも子どもたちの心の育ちを
喜びあいながら一緒に過ごして参りましょう。
園長 玉井史恵
2022.11.01
心にしみこむ

私はカトリックの幼稚園で育ちました。
小学校に入ってからは宗教にふれることもなく過ごしてきましたが、
幼稚園の先生になりたいと思い学校を選ぶとき、
ごく自然にカトリックの学校に行きたいと思いました。
心の中で眠っていた神様が目を覚ましはじめたような感覚でした。
学校では宗教の時間があったり、クリスマスのミサがあったり、
シスターがいらっしゃったり、中には面倒だという友人もいましたが、
私は何の違和感もなくむしろ懐かしい光景に感じたことを思い出します。
確かに宗教の時間は退屈ではありましたが…。
頭で理解する神様ではなく、幼児期に心に染み込んだ神様の存在は
やはり大きかったのだと今になって思います。
話は変りますが私が小さい頃、明治生まれの祖母は
毎日食事の後片付けを自分の役割としていました。
今のお母さま方には想像がつかないと思いますが、
昔の炊飯器は窯内部の加工がされていませんので
ご飯粒が沢山ついて残ってしまいます。
(飯ごうでご飯をたくようなものでしょうか)
祖母は後片付けの時、いつもお釜に水を入れくっついて残った
ご飯を釜からはがし、それを手ですくって食べていました。
それがとても美味しそうに見えた私は
「私も食べたい!」と言って食べてみましたが、
冷たくふやけたごはんは決して美味しいものではありませんでした。
『どうして美味しくないのに毎日食べるのか』と聞いた時
『一粒の米も捨ててはいけないこと』を教えられました。
毎日目にしていたこの祖母の姿は私の中で事あるごとによみがえってきます。
そのためか、食べきれない時に残すことはあっても、
ご飯粒を茶碗にくっつけたまま終わりにすることにとても罪悪感があります。
(だいぶ矛盾していますけど…)主人は私が残したものを
「もったいないと言って食べ」私は主人がもう取れないと言って
残そうとするご飯粒を「もったいない」と集め「はい食べて」と渡す。
「どっちがもったいないんだ?」「どっちも!」
と笑い合うこともしばしばで、お互い食べ物を大切にする気持ちはあるけれど、
育った過程でしみこんだものが違うんだな~と感じます。
子どもの頃に経験したこと、感じたこと、教えられたこと、
というのは本人が意識していなくても確実にその人にしみ込んでいるのでしょう。
さて今年もクリスマスが近づいてきました。
毎年この時期になると、今年はどんな思いで待降節を
過ごしたらよいだろうかと考え始めます。
(考えようとしている時点でもうダメダメなのだと思いますが…)
今年は子どもたちと食べ物のない方たちのことを考えて過ごしますので、
私も、食べものを大事に、作りすぎない、買いすぎない、
最後まで食べきる、捨てない、ことを意識して過ごしたいと思います。
子どもたちも、自分以外の人たちに心を向け、
自分にできることを考えながら過ごしていきます。
『隣人を愛する』 難しい言葉は忘れてしまったとしても、
この経験が一人ひとりの心の中に深くしみ込み、
優しさの根となっていきますように…。
園長 玉井 史恵
2022.09.05

親子の時間
園長 玉井 史恵
先日NHKの 『チコちゃんに叱られる』
で 親子が一緒に過ごせる時間についての
放送をしていました。
数年前にも放送していたので、
ご覧になった方も多いかもしれませんが…。
親が子と生涯で一緒に過ごせる時間は
母親で7年6か月 父親で3年4か月だそうです。
そのうち年少で入園するまでに18%の時間が終わり、
幼稚園卒園時には32%、小学校卒業時には55%、
高校を卒業して親元を離れると、
70%の時間が終わっているそうですから、
その時点で残りは30%ということになります。
私自身のことを振り返ってみると、
幼稚園に入るまではほぼ1日中一緒に
過ごしていましたが、
幼稚園に入ると、降園してから寝るまでの数時間、
小学校に入ってからは親より友達と
過ごす時間を求めるようになり、
親子でべったり一緒にいる時間は
どんどん減っていきました。
そして私がフルタイムで仕事を始めると、
平日は食事と入浴の時間くらいしか
一緒に過ごす時間がありませんでした。
本当にテレビで言っていた通りです。
子育て中、子どもは大好きだけれど、
たまには一人で好きなことをしたいと思ったこともしばしば。
でも子どもが巣立った後は、
子どもと過ごせる時間のありがたさを
ひしひしと感じるように…。本当に身勝手なものです。
私の娘は大学から東京で一人暮らし。
その後結婚して現在は神奈川県住まい。
それでも頻繁に行ったり来たり1年に
何度も会えることが当たり前でした。
そんな当たり前の日々が、
コロナウイルスの出現で一変しました。
会いたいけれどいろいろなことを考えると
帰ってきていいよと言えない。
娘も帰りたいけれど帰れない。
そんな日々が続きました。
今年の夏は3年ぶりに娘が夫婦で帰省をし、
(検査を受けて)久しぶりの家族団らんができました。
娘が今ハマっている宝塚のDVDを
夜中まで一緒に見て盛り上がり、
仕事の話をしたり、
ネットをみながら欲しい物の相談をしたり、
丸2日間楽しい母と子の時間を過ごしました。
娘と父親も仲がよいのですが、
母娘の話題にはついてこられず…。
父親との時間の短さをこれまた実感しました。
チコちゃんに叱られるではもう一つ、
子が親と過ごせる時間についても触れていました。
私が子なら、自分の親と過ごせる時間は、
1年で24時間 まる1日程度(一緒に住んでいない親子)
だそうです。
親が生きる残り年数(平均余命)が10年なら10日、
20年なら20日ということですが、
コロナ禍になり、
この日数すら危ういのではないかと思ってしまいます。
私に残された娘との時間は? 両親との時間は?
コロナ禍にあって、また今度、そのうちに、
ができないことを経験しました。
どんなに願っても今が永遠に続くことはありません。
巻き戻すことのできない時間、
後悔のないように、
一緒に居られる時間を慈しんで過ごしたいと思った夏でした。
皆さんはお子さんとの限りある時間を
どのように過ごしたいですか…。
2022.07.30
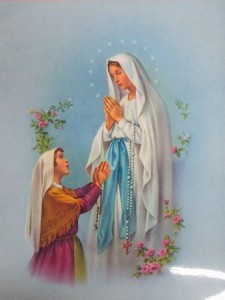
大丈夫 だいじょうぶ
園長 玉井史恵
2022年5月、病気療養中だった私たちにとって
とても大切な先生が天に召されました。
マリア幼稚園が大好きで、闘病中も
『今日はクリスマス会だね』
『今日は卒園式だ』『みんな頑張っているかな』
と幼稚園のことばかり気にかけておられたそうです。
私たちは毎朝 朝礼で当番の先生が聖書の福音を読み、
祈りを捧げてから1日を始めていますが、
訃報が届いてから毎朝の祈りの中で、
その先生との思い出が語られるようになりました。
思い出されるのは彼女から掛けて頂いた言葉や、
子どもへ対する接し方や、
保育に対する思いや、夫婦げんかの愚痴話まで…。
はじめは悲しくて悲しくて…言葉につまりながら…
毎日涙の朝礼でした。
私も含め先生方は思い出を語る中で、
彼女から沢山のものをいただいていたことに気づかされ、
悲しみでいっぱいの祈りから、
感謝の祈りへと変わっていきました。
三浦綾子さんの本の中に書かれていた
『わたしたちが一生を終えてこの世に残るものは、
生涯をかけて集めたものではなく、
生涯をかけて与えたものである』
という言葉を思い出しました。
まさにこの言葉のとおり、
彼女が私たちに与えてくださった愛が、
先生方一人ひとりの心の中で
生きていることを実感しました。
そんな中皆に共通していたのは、
どんな時も、誰にでも「大丈夫、大丈夫」と
言っておられた言葉でした。
ご自宅で療養中も最後まで笑顔を絶やさなかったと伺いました。
皆に心配をかけないよう「大丈夫、大丈夫」
をご自身も最後の時まで貫き通していたお姿が目に浮かびます。
先生が亡くなってから、
今までお聖堂にあまり姿を見せなかった子が
毎日祈りにくるようになりました。
「先生喜んでくれるかな?」と
一生懸命摘んでくれたシロツメ草。
悲しむお母さんに
「先生はいつも心の中にいてくれるから大丈夫だよ」と
声を掛けてくれたお子さん。
子どもたちの中にも先生の愛は生きていました。
もっともっと幼稚園で子どもたちの笑顔をみていたかったはず…
もっともっと皆とたわいもない話で笑いたかったはず…。
彼女から与えてもらったことを、
残された私たちが周りの人に分け与えていくことで、
先生が私たちと共に生きてくださることを信じて、
彼女の分まで皆で頑張っていきます。
訃報を受けてから、年長の子どもたちが歌ってくれた
~マリア様の心~ を動画に撮って
子どもたちの歌で先生を天国へお送りすることができました。
「私は大丈夫、私の家族のために祈ってね」
先生から託されたの最後の願いでした。
皆でその願いを忘れずに祈り続けます。
先生への感謝を込めて…。
2022.05.01

みまもる
園長 玉井史恵
私の娘はこのマリア幼稚園に通っていました。
お昼寝が嫌いで、昼寝中におしゃべりしすぎては、
「今日ね~先生に廊下でおしゃべりしてきなさいって言われたの~」
(今はそういう指導はしません…ご心配なく)
「また寝なかったの?」「そう~!」
とケロリと言ってのけるほど、マイペース。
そんなことがあっても幼稚園が大好きで
一度も嫌だと泣いたことがありませんでした。
小学校入学後も学校が嫌だと言うこともなく
喜んで通っていました。
そんな娘が小学校5年生の時に
学校にいくのが辛くなりました。
それは5年生の時、クラスの目標が
ドッジボールでのクラス作りになったことから
はじまりました。
はじめのうちはまだ楽しいと思えていたようですが、
学校外の大会にクラスとして出るようになり、
勝つことが全てのクラス作りの中、
「ドッジボールがうまくできない、
朝も、休み時間も、昼休みも練習しないといけない、
毎日ドッジボールばかりで学校が楽しくない。」
そんなことを言い出しました。
「ドッジボールなんてできなくたっていいじゃない、
休み時間だって好きなことをすればいいじゃない」と言っても、
練習にいかないと責められる…と。
子どもの話だけではなんともわからないと思い、
解決の道を探りましたが良い道はみつからず
切ない日々が続きました。
そして6年生になった時
「そんなに嫌なら学校に行かなくてもいい」と娘に言いました。
(今思えば私が楽になりたかったのかもしれません…)
しかし返ってきた言葉は
「そんなことをしたら、負けたことになるから学校には行く!」と。
とても驚きました。
相変わらずドッジボールでの毎日に疲弊しながらも、
なんとか卒業の日を迎えることができました。
卒業式の日、音楽の先生や保健の先生に
がんばったねと声を掛けていただいた時、
こうして影で支えてくださっている先生が
いてくださったお陰で娘は学校に通うことができたのだと、
感謝の気持ちでいっぱいになりました。
今でも『あの時娘が学校に行かないと言っていたら、
どうなっていたのだろうか』と思う時があります。
親として言ってよい言葉だったのかどうかもわかりません。
一番辛かった時神父様から
「神様は乗り越えられない試練は与えない」
という話をお聞きしました。
「今は試練の意味がわからないかもしれないが、
必ずわかる時が来る。神様は困難を取り除くのではなく、
乗り越える力を与えてくださる。
だから乗り越えられるようにと祈りなさい」と
話してくださった言葉が
私たち親子の心の支えになりました。
そしてその時ほど神様の存在を近くに感じたことはありませんでした。
今もその頃のことを思いだすと涙が出ます…。
でも、その出来事があってから、
私の考え方は大きく変化しました。
今になれば、あの試練は娘のためではなく、
私のためだったのだと思えてなりません。
今はまだ毎日泣いて登園しているお子さんもいます。
『なぜこんなに…』『いつまで…』と
切ない気持ちで送りだされている方もいらっしゃると思います。
親は子どもの力を信じて見守ることしかできない時もあります。
見守ることの辛さもよくわかります。
辛いときはどうぞ話にきてください。
子どもたちはこれから先様々なことにぶつかっていくことでしょう。
そんな時は困難を乗り越えられるよう
神様に祈り求めながら、
強い心と優しい眼差しで、
子どもたちを見守っていきましょう。
2022.04.14

きずな
園長 玉井史恵
3月、卒園間近の子どもたちが「私は○○小学校」
「ぼくは○○小学校」「私も同じ、一緒だね!」
と楽しそうに話していましたが、
一人の女の子が「私はお引越しをするから、
みんなと同じ学校に行かれない…」と寂しそうに言いました。
すると男の子が「いつもマリア様が一緒だから大丈夫だよ」と言い、
それを聞いた女の子は「そうだね」とにっこり。
なんて素敵な会話でしょう。
わたしたちが、毎日を充実させて
いつくしみにあふれた日々を生きるには
「自分自身との絆」
「他の人との絆」
「人間を超える存在との絆」
が必要だと言われたことがありますが、
この子どもたちの中にはすでに
この3つの絆ができていることを感じました。
さて今年は45名の新入園児さんを迎えて
新年度をスタートすることができました。
新しいクラスのお友だちとの出会い、
新しい先生との出会い、
はじめて幼稚園に入ったこどもたちは神様との出会い、
それぞれの出会いがまた新しい絆につながっていきます。
しかしすぐに新しい環境に慣れるお子さんもいれば、
環境の変化をすぐには受入れられないお子さんもいます。
適応していく時間は一人ひとり違います。
親とすれば早く慣れてくれた方が安心ですが、
そうそう思い通りにならないのが、現実です。
以前、未満児から年少に進級した一人の子どもは、
毎日毎日大泣きで、何もしようとしませんでした。
担任はどうしたら泣かずにいてくれるのか必死でした。
いろいろ手を尽くし、言葉を尽くしましたがうまくいきません。
担任以外の先生が一緒に過ごせば落ち着きますが、
担任の所に戻るとまた大泣き…
でも担任がその子の泣きたい気持ちを受け入れ、
泣いても大丈夫だと双方が思った時、
その子は泣かなくなり以前のように
何でも一人でやるようになりました。
その子は他の誰とでもなく、
担任と絆を結びたかったのだと思います。
このように、子どもたちも新しい人たちと
心を通わすために必死なのです。
そして、そんな子どもたちの姿から
絆は子どもたちの心を強いものにし、
すべての原動力につながっていることを実感させられます。
ですから、あせらず、人と比べず、
一人ひとりの成長の時間をじっくり待ちましょう。
そして1年を終えた時
また素晴らしい絆でむすばれたことが実感できますように。
今年度もよろしくお願いいたします。
2022.03.01

いったり きたり
園長 玉井 史恵
園長就任から1年、
先日ある保護者の方が
「1年経ちますね、
入園式の日の先生は普段の様子と随分ちがっていて、
緊張しているんだな~と思いました」と
笑いながら話してくださいました。
今でも皆さんの前に立つ時は緊張しています。
小心者で大勢の前は得意ではないのです…。
それならなぜ先生になったのかということですが…(笑)
そんな私がなんとか1年過ごしてこられたのは
保護者の皆様が温かく見守り支えて下さったお陰です。
それに加えマリア幼稚園の教職員の
チームワークの良さがあった
(手前味噌ですいません)お陰です。
皆様1年間本当にありがとうございました。
私は4月から毎朝「おはよう」と
声をかけながら廊下を回っていました。
ひと所に長居をすると朝の用意や着替えの
邪魔をすることになってしまうので、
気をつけてはいるのですがついつい時間を忘れ、
職員室から「ほらまた帰って来ない」と
防犯カメラで居場所を探され
「園長先生戻ってきてくださ~い」と
放送がかかることもしばしば…。
そんな毎日のひと時は何よりも楽しい時間で、
幼稚園にいるな~と実感させてもらえる時間でした。
声をかけても下を向いていた年少さんが
笑顔で抱きついてきてくれるようになった日、
朝の着替えが嫌で廊下を走り回っていた年少さんが
得意げに一人でやったよと見せてくれた日、
2階に一人で上がれず「園長先生一緒に行って~」と
泣いていた年中さんが
「お友だちと一緒に行くからもういいよ!」と
私と繋いでいた手を離した日、
一人では話せなかった年長さんが、
元気のよいお友だちにつられて
お尻をたたきに来たり、くすぐりに来たり、
じゃれついてくるようになった日、
朝のひと時の中にも一人ひとりの成長がありました。
そんな子どもたちの成長の一番の支えになっていたものは、
安心感だと思います。
幼稚園に行ってお母さんやお父さんと
離れていても大丈夫という安心感。
この先生だったら私のことを
受け入れてくれるという安心感。
一緒にいてくれるお友だち、
一緒に遊べるお友だちがいる安心感。
このような安定した気持ちの中で
子どもたちは安心して自分を出していくことができます。
そして大人との関わりに満足した子どもは、
必ず自分から手を離して歩き出します。
しかし子どもの成長は一直線ではありません。
調子がいいかと思えば立ち止まり、
止まっているな~と思えば急に上昇し、
そうかと思えば急降下だってあります。
魔の2才児と思春期の間にだって反抗期は訪れます。
そうやって 『いったり きたり』
しながらも子どもたちは確実に成長していきます。
その間、環境も変わりますし、周囲の人も変化していきます。
変わらず関わっていくのは家族だけです。
ですから
『何があってもしっかり受けとめてくれる家族がいてくれる』
という安心感がどれほど大切なことでしょう。
1年生になるお子さんだけでなく、
皆1年間慣れ親しんだ環境から、
新しい環境へ変わる4月がやってきます。
子どもの心の『いったり きたり』が増える時。
いったりきたりも大切な成長過程と思い、
慌てず、いら立たず、
大きく手を広げて一緒に受けとめて参りましょう。
ご心配なことがありましたらいつでもお声がけください。
2021.11.08
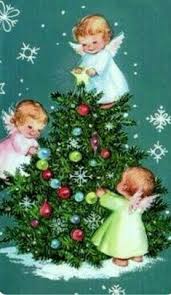
ご大切に
園長 玉井 史恵
私がマリア幼稚園に就職した当時、
神様は厳しい方という教えでした。
悪いことをすれば神様に叱られる。
良いことをすれば神様に褒められる。
と子どもたちにも伝えていました。
「誰も見ていなくても神様がみているから、
悪いことはしないで。」という感じでしたので、
私にとっての神様は、良い悪いの裁き手のような方でした。
しかしその後、前々園長の秋元神父様をはじめ、
多くの神父様が教えてくださった神様は違いました。
神様は『アッバ』おとうちゃん(親愛なる情を込めて)だと
教えてくださいました。
おとうちゃんですから、遠くにいる方ではなく、
私たちを見張っている方でもなく、
いつも私たちのそばで見守ってくださる方であると。
そして私たちが間違ったことをしてしまった時は、
叱るのではなく悲しむ方なのだと教わりました。
その神様の子として、イエス様はお生まれになりました。
そしてイエス様は世界中の人々に愛することの
大切さを教えてくださいました。
キリスト教が日本に入ってきたとき、
日本人は「愛する」という言葉の意味を正しく受け入れる
ことができなかったため、『ご大切』
という言葉に言いかえて伝えられていたのだそうです。
マリア学園の教育理念は
『わたしがあなたがたを愛したように、
あなたがたも互いに愛し合いなさい』
(聖書に書かれているイエス様の言葉)ですが、
それは
『私があなたたちを大切にしたように、
あなたがたも互いをご大切にしあいなさい』
という言葉になります。
愛しなさいと言われるより、
ご大切にしなさいと言われたほうが、今の私にもハードルが下がって、
できそうな感じがしてきます。皆様はどうですか?
しばらく前に年中の女の子が
一人で御聖堂の椅子に座っていました。
どんなお祈りをしにきたのだろうと、
私はその子からは見えないところでそっと耳を傾けていると、
「神様、今日はお友達と仲良く遊びました。ありがとう…」
と祈りはじめました。
そのあとも少し祈りは続いていたのですが、
小さな声でしたので残念ながら聞こえませんでした。
でもその祈りを聞いたとき、小さなロウソクの火がともったように、
心の中がじんわりと温かくなりました。
その姿を思い出すだけで、今も幸せな気持ちになります。
今年もクリスマスが近づいてきました。
毎年この時期になると、子どもたちにイエス様をお迎えするために
心のプレゼントをためましょう。と話しをしながら、
私も何かよいことをしなくては!と、
急いで良い人になろうと努力をはじめていましたが、
手っ取り早くする良いことなどたかが知れています。
この女の子のように、誰かに見てもらうためではなく、
褒められるためでもなく、自慢するためでもなく、
そっと神様だけに祈った、そんな素直な心が愛の心なのだろう。
と気づかせてもらった気がします。
私もそんなふうに、周りの人に気づかれないくらいに
そっと人を大切にしながら、クリスマスを迎える心の準備をしていきたい。
と思わせてくれた出来事でした。
ここに書いている時点で「そっとではないね…」
と神様は笑っておられるかもしれませんが…。
世界中の人々が、
互いをご大切にし合いながら、
温かい気持ちでクリスマスを迎えられますように…。
2021.09.28

転ばぬ先の杖 園長 玉井 史恵
私の娘は、このマリア幼稚園に通っていました。
(その頃私は仕事を一度退職し、主婦をしていました)
年少の運動会の時、それは それは 嬉しそうにリズムを
踊っていた娘でしたが、玉入れときたら、
一人玉入れのかごに背を向け、しゃがんだまま後ろに玉を
投げていました(笑)一人っ子ということもあってか、
とにかくマイペース。慌てるとか、人と競うとか
そういう気持ちは全くというほど持ち合わせていなかった娘です。
親としてはこんな娘で大丈夫かと心配で
「早く早く」を繰り返し、間に合わない時は手を出していましたが、
本人は全く困った様子もなく毎日楽しそうに幼稚園時代を過ごしました。
そんな娘が小学校にあがってじきに
「今日ね~トイレから戻ってきたら、教室に誰もいなくて、
泣いてたら知らない先生が畑に連れていってくれたの…」
という出来事が起こりました。のんびりしていると
置いていかれるという経験をした娘。
またある日先生から「バスに乗り遅れたので迎えにきてください」
と電話が…(冬だけ低学年はバスがありました)
乗り遅れた理由は教室で手袋をさがしていたのだと…。
また別の日、ランドセルのふたをきちんと閉じなかった娘、
下校中、友達とふざけながら歩いていて、
下を向いた途端ランドセルの中身が川の中へ…。
友だちに手伝ってもらいながら、
びしょ濡れの教科書を拾って帰ってきました。
こんな小さな失敗や困った、を繰り返しながら
娘は少しずつ変わっていきました。
そして親の私も娘の姿を見ながら、
いくら親が何か言っても、本人が本当に困り、
こうしようと思わない限り変わることはないと実感しました。
(それでも低学年の困った、はかわいいもの。
この後最大の困ったに出会いますが、その話はまたそのうちに…。)
親としてはついつい、子どもが困らないように
先回りして手を出したり、声をかけたりしたくなります。
その方が親は楽ですし、心配もいらないからです。
でもそれはその場限りでしかないことを実感した私は、
命にかかわらないことに対しては、すぐに口出しをしない、
じれったくても待つということを意識してきました。
とは言うものの、時間があって子どもの姿が目に入れば
ついつい口を出したくなりますし、仕事を始めて時間がなくなると、
今度は待っていられず口やかましくなってしまう、
なかなか難しいものでしたが…。
さて、幼稚園の生活の中でも、子どもたちにとって
小さな困った は起こります。
お箸を忘れた子どもが、職員室に「お箸貸してください」
と借りに来ます。1回目は泣きながら借りにきた子どもも、
3回目くらいになると堂々と(笑)借りにきます。
忘れても借りれば大丈夫という経験があるからです。
これは箸だけの話で終わらず、忘れ物をしたときは
何か違う方法で対処すればいい。という考え方に
つながっていくはずです。
忘れ物をしたことのない子どもより、
したことのある子どもの方が、実はよい経験を
しているように思います。
こう考えると、たまには忘れ物の経験もいいものです。
忘れ物に限らず、小さな 『困った』にぶつかり、
困ったことを解決する度に 『こういう時はこうすればいいんだ』
『困ったことがあっても大丈夫』と子どもたちは学んでいきます。
その積み重ねが、この先『大きな困った』に出会った時、
必ず乗り越える力になるはずです。
クラス替えなど環境の変化にも慣れて落ち着いてきた2学期、
大人の私たちが先回りして、手や口を出すことで、
子どもの学ぶチャンス、成長するチャンスを奪ってしまわないよう、
意識して過ごしてみませんか。
『転ばぬ先の杖』 ということわざがありますが、
~ 転ばぬ先の杖 出さないことも 親の愛かな ~
と思います。






